手のひらに乗るほどの、小さなあなたになって
荼毘に付したその日から
次はこのお骨をどこに置こうかということになりました。
わがままな話かもしれませんが
亡くなったあの子の魂は
私が死ぬまでずっと、隣にいてほしい。
ただ、そう思うだけでした。
あの子には重度の障がいがあって
食事も着替えも移動も
すべて介助なしには生活することができませんでしたので
あの世へ旅立ってしまっても
お世話してくれる人がいなければ困っちゃうのです。
家族の中でも
誰も「お墓に…」という声は出てこなくて
このままお家で一緒に過ごそうね、と
自然な流れになっていました。
手元供養という、時代がくれたやさしい選択
世間一般の流れなら(仏教の慣習でいえば)
四十九日を過ぎれば忌明けとなり
魂があの世へ旅立つ節目として、お墓に納骨を行います。
夫の両親は
「お墓はどうするのか?」とか
「いつまでもそばに置いておかないほうが…」とか
夫には色々と言っていたようです。
その気持ちはありがたくて
その優しさもちゃんと感じ取りました。
だけどあのときの私には
その言葉がどこか遠くから響いているように感じました。
昔の世代にとっては、
お墓に納めてこそ「区切り」がつくという感覚が
自然なことだったのだと思います。
だけど今は―――
暮らしの形も
家族の形も
祈りの場所もかたちも、少しずつ変わってきているようです。

「手元供養」という考え方は、
そんな時代の中で生まれた
やさしい選択のひとつだと思います。
実際、わたしも「手元供養」というスタイルがあって
助けられたと思っています。
お墓に入れなくても、
手の届くところに置いておくことで、
わたしの中ではあの子と“今”を生きている感覚があるから。
かたちは違っても、
想いの深さは何も変わらない。
時代が変わっただけ。
祈りの場所が、少し近くなっただけ――。
暮らしの中にある祈り=光と香り
朝がくると
お姉ちゃんと一緒に寝ていたあの子を受け取り
いつもの場所に戻します。
雨戸を開けて朝陽が入ってきて
「おはよう」「今日は寒いね〜」と声をかけます。
1日の始まりとして、アロマキャンドルを炊くのですが
我が家は上の子達がまだ小学生で
本物の火を扱うのは危険なため
キャンドルウォーマーを使っています。
created by Rinker¥4,980 (2025/11/03 23:53:23時点 楽天市場調べ-詳細)タイマー付きで、調光機能あり。
明るさ=加熱の強さで、キャンドル消費・香りの強さに影響します。
実際の我が家のキャンドルウォーマーです。

とっても温かみのある色でしょう?
家族みんな、仏壇のろうそくに火を灯すような感覚で
このアロマキャンドルのスイッチをいれます。
朝起きたとき
夜眠るとき
あの子の生活リズムに合わせてスイッチを入れます。
created by Rinker¥6,402 (2025/11/03 23:53:23時点 楽天市場調べ-詳細)淡いラグジュアリーなサンダルウッドの香りに心が優しく包まれます。
我が家のアロマキャンドルは
約2年前に購入しましたが…

1日数時間、毎日焚いていても
まだまだ、9割は残っているという驚異的なコスパです。
値段はやや張りますが、すごーく長持ちするという優れモノ。
そして火をつけてみると
この木芯、パチパチと音をたてて燃えるのです。
静かな時間に、1人であの子を想いたい時は
ウォーマーではなく火を灯して
骨壺を抱っこして
ゆらゆら揺れる火を眺めています。
以上、私の手元供養アイテムの一部をご紹介させていただきました。
それぞれの、祈りのかたち
手元供養の形は
人の数だけあるのだと思います。
お墓に納める人もいれば、
家の中でそっと寄り添う人もいる。
どれが正しいということではなく、
その人にとって“心が落ち着く形”がいちばん。
もし、「どうしようか」と迷う人がいるなら―――
無理に急いで答えを出さなくてもいいと思うのです。
時間が流れていく中で
自分なりの答え、その人らしい祈りの形が見つかるはずです。
わたしはただ手放せずに
そばにおいて置くことを決めた、ただそれだけのこと。
それがふと、いつか何か、変わるかもしれない。
でもそれは、誰にもわからない。
今はただ、光と香りの中にあの子を感じるこの時間が
今日を生きる力になっています。
どんな形でも、想う気持ちは自由でいい。
その人らしい祈り方が、
いちばんやさしい供養になるのだと思います。



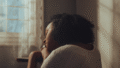
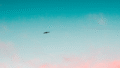
コメント